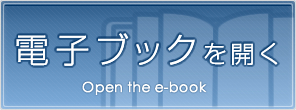戦国時代の京都の史跡を歩く13コース page 3/12
このページは 戦国時代の京都の史跡を歩く13コース の電子ブックに掲載されている3ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
? 1 ?ていた。「フロイス」の報告書に書かれている。東へ歩み新京極に「タコ」の薬師堂がある、この通りの名の由来である。面白い伝説がある、参拝してみよう。これより寺町通を北へしばらく歩くと、御池通手前に現....
? 1 ?ていた。「フロイス」の報告書に書かれている。東へ歩み新京極に「タコ」の薬師堂がある、この通りの名の由来である。面白い伝説がある、参拝してみよう。これより寺町通を北へしばらく歩くと、御池通手前に現在の本能寺がある。秀吉の京都都市改造によりお土居の内側に寺町が造られ移転した。信長所蔵の茶道具類や書状を収蔵展示する。寺町通を御池通を越えて北へ歩いてみよう。二条は梶井基次郎の名作「檸檬」の舞台。少し歩くと革堂(こうどう)。ここの「幽霊絵馬」の特別公開は1年のうちで8月22日と23日のみ。この変わったお寺から下御霊神社へ、皇室の政変での方々を神として祭っている。早良(さわら)親王、井上(いがみ(いのえ))内親王、他戸(おさべ)親王達がそれである。丸太町を過ぎると右側に新島旧邸の洋館が迎えてくれる(見学可能)。大河ドラマ「八重の桜」の八重が、襄と暮らしたところだ。左側は京都御苑の林が拡がっている。寺町御門から苑内を歩いて北の今出川御門へ抜けても良い。左に梨木神社を見て、今出川通を更に北へ歩くと、山中鹿之助墓のある実泉院(本満寺塔頭)、さらに北上、阿弥陀寺に着く。清玉上人が本能寺の変の際、遺体を処理し運んだという伝承がある寺である。焼け跡から回収した遺品も、この寺に多く収納されている。この北には山門が「額縁」となり比叡山が見える、金森宗和ゆかりの寺(天寧寺(てんねいじ))とかがあり、ここも寺町の名残が良く分かる辺りである。東へ出れば鴨川の景色が素晴らしい。P11~12コース 4JR二条駅~黒田如水邸跡コースJR嵯峨野線二条駅へは、JR京都駅の西ホームから乗車。秀吉が京都改造した時、作ったお土居の上をこの軌道は走る。JR二条駅は、平安京の朱雀門のあった場所である。駅前の千本通は当時の朱雀大路。駅前を東側に向かって歩くと左側に、池に赤い橋がある神社の様なお寺がある。真言宗「神泉苑」である。五位鷺(ごいさぎ)の故事もここから生まれた(神泉苑の善女龍王社の北にある中島には五位鷺が棲むという)。「一願成就橋」を渡ると弘法大師が雨乞い合戦をした有名な遺跡、平安京の唯一残る庭園の跡だ。この苑を北へ抜けると寺門(北門)がある。近江国の膳所城(ぜぜじょう)の大手門が、唯一ここに残る。向かいにお堀が見える。二条城である。東側に正門・大手門、敵に簡単に打ち破られない為に、門のところどころに鉄板を組み込んだ。「筋金入り」と言う言葉はこの門から生まれたという。入城見学2時間位である。ここより北へ歩むと板倉勝重邸跡、西に歩むとこの辺りは京都所司代のあったところ。二条城北西に二条公園があり、北縁の「鵺(ぬえ)大明神」は、源三位頼政のぬえ退治の遺跡である。この辺りは所司代の処刑場跡で、この隣のビルで「怨念」のうめき声が夜な夜な聞かれたところ。丸太町通を横切り、知恵光通を北へ少し行くと松林寺(聚楽第の外堀跡また幕末見廻組の佐々木唯三郎の宿所)、大宮中立売に聚楽第址碑)→大宮通の二つ東の猪熊通を一条へ、黒田如水邸跡だ。東北へ歩むと晴明神社、この東に怪奇スポット一条戻り橋だ。一条戻り橋から北へ歩み今出川を東へ北側に白峯(しらみね)神宮、四国の白峯(しろみね)から崇徳さんがここに戻られて祀られている。ここは「蹴鞠」が家業の公家・飛鳥井さんの領地で、今はサッカーの神様としての人気スポットだ。さらに東進すれば地下鉄今出川駅。 P13~15コース 5 建勲神社から大徳寺、そして寺之内へ市バス停「大徳寺前」下車、すぐ側に大徳寺。寺内には戦国武将とかかわりの深い塔頭寺院が多くある。庭園や茶室も個性豊かなものが多い。船岡東通りを南へ徒歩3分、建勲神社の表参道大鳥居に至る。大鳥居より約120段の石段を上ると社務所に至る。徒歩約7分である。祭神は織田信長、信忠を配祀する。鞍馬口通りを東へ行くと、島津製作所の横に紫式部と小野篁の墓がある。堀川通から上御霊前通を東通すると妙覚寺。往時は二条衣棚(衣棚押小路)にあり、上洛の織田信長が常宿とした。堀川の西側には「おりべ寺」、古田織部の墓のある興聖寺。南向かえは本法寺、何しろ寺だらけの町が京都だ。「表千家」「裏千家」ゾーンを通って報恩寺(秀吉の鳴虎)。黒田官兵衛の子・長政の京都宿舎であり、客殿に黒田長政が死去した部屋が残るという。油小路を下がり、本阿弥光悦屋敷跡碑。堀川今出川のバス停留所は近い。P16~17コース 6 東山ウォーク、京阪三条駅から清水寺へ京阪三条駅から三条大橋から北山を眺めながら、北側を渡る橋詰は高札場跡地、広場が今も残る。幕末期、近藤勇の首事件が頭に浮かぶ。少し歩み南側へ渡る、目の前に高瀬川が流れ、桜並木が川に沿って続いている。ここにお寺がある「瑞泉寺」。秀吉は、関白秀次の一族を女子供まで皆殺しにして三条河原に埋め、「畜生石」という塚が建てられた。これは時と共に失われたが、角倉氏が運河建設工事の際発見し、ここに寺を建てて鎮魂した。それまでこの辺りは「秀次行列のゆうれい」が度々現れていたという。この東側の通りは先斗町。「ポント」は、ポルトガル語の土手という意味である。お土居の上に花街が発展したところだ。先斗町歌舞練場の建物がレトロで美しい。下って行くと、夕刻には舞妓さんや芸妓さんにすれ違う場所だ。四条へ出て、鴨川を渡ると南座を過ぎ、右に古いお寺(仲源寺)ここは目疾地蔵と言われ市民の信仰厚き寺。戻って大和大路を下り団栗通を東に向かい、正伝永源院(織田有楽斎の墓)そして、お色気漂う祇園甲部の中の歴史跡をたどり、八坂神社石段下へ着く。参拝して円山公園の名物枝垂れ桜を右へ「ねねの道」を歩くと祇園閣(祇園祭の鉾のような建物)が眼に入ってくる。ここは大雲院といい、織田信長・信忠父子、石川五右衛門の墓がある面白いお寺。市内からここへ移転してきた大倉別荘の跡で、大倉財閥のなごりが祇園閣だ。やがて高台寺の塔頭「月真院」、その前に高台寺党の駒札が建つ。新選組を分離しその後、油小路事件の悲劇につながる史跡だ。圓徳院は北政所のお住いの地。その東に高台寺があり、北政所はここ眠っておられる。大きい霊山観音像を左に見て、段坂を下る。目の前に「八坂の塔」が、「夕景西山に沈む太陽と八坂の塔は絶景」である。ここから二年坂、三年坂を登る。三年坂(産寧坂が正しく)は、清水の子安観音に安産祈願に市民がよく参拝する参道で、子安観音は産婦の安全の寺。子供の時よく母からここで「こけたらあかんえ」と何回も言われた事を思い出しながら七味家へ辿り着いた。ここを左へ登って行くとお土産屋さんが両側に並ぶ、少し歩くと清水の塔が見える。右へ廻れば音羽の滝と舞台の下に行く。滝水を酌む人の行列が見えてくる。P18~19コース 7 「報土寺」、黒田官兵衛のただ一人の妻・光(てる)の墓から北野天満宮JR円町駅、円町とは珍しい地名である。これは平安京の時代、右獄という獄があった所で、獄門があり平治の乱の際、藤原信西の首が晒された。秀吉が天下統一し京都を改造、お土居を作った際、この獄を移転出来ず、お土居の「そで」囲いに獄を設けたところから、囲む円町となったのである。少し丸太町通を西へ、紙屋川が流れている。古代から紙の生産拠点であった川の名で、下流は天神川と呼ばれている。法輪寺(達磨寺)とか竹林寺とか、ここも寺町が形成されている。竹林寺は、明治期都市開発工事の際に、「禁門の変」の際の処刑者を右獄に埋めた遺骨が出土、刑死者平野国臣他の認識表が衣服に残っており確信され竹林寺に埋葬された。この近くに元阿弥陀寺清玉上人が本能寺より信長の遺骨を葬った寺跡が残っている。仁和寺街道西へ七本松上ル、立本寺には島左近の墓がある。左近は関ケ原よりこの地に逃れ僧としてこの寺で一生を終えたと言われている。この北側は水上勉の「五番町夕霧楼」で有名になった花街五番町。隣の四番町には遊女投込寺「報土寺」という大きいお寺もある。黒田官兵衛のただ一人の妻であり、才徳兼備であったとされる、光(てる)の墓があり、肖像画も伝来し京都国立博物館に委託されている。秀吉や官兵衛が訪れた過去帳も現存しているという。光(てる)の建立した照福院という塔頭があったが、報土寺が相国寺付近から移転した際に消滅している。北へ歩けば上七軒花街だ。上七軒は北野天満宮建替えの際、その廃材で七軒のお茶屋を設けた、これが花街となった。北野天満宮は秀吉の北野大茶会で有名になったところ、お土居跡が神社の境内に残る。西大路通を下ると、地蔵院(秀吉の椿で有名な椿寺)がある。紙屋川に沿って円町に戻るのも良い。